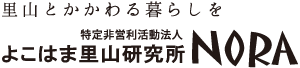第189回 田んぼと高度経済成長
2024.5.30いしだのおじさんの田園都市生活
1960年代、
俺が、産まれて、幼少期を過ごした、
その時代とは、何だったんだ、らう?
1945年、敗戦。
1951年、講和。
1955年、55年体制。
1956年、水俣病。
1960年、安保闘争敗北。所得倍増計画。
1964年、東京オリンピック。
1966年、成田闘争、始まる。
同年、 ビートルズ来日。
1967年、米自給、なる。(一人あたりの消費量100㎏/年→2020年には53㎏)
同年、 「帰ってきたヨッパライ」
1969年、安田講堂陥落。
1970年、大阪万博。
同年、 減反。
いわゆる、高度経済成長。
1961年、石田周一、「ぼうやが生まれた」。
1965年、アパート転々、から、の、辻堂での団地暮らし。
1967年、田園青葉台団地。
1973年、青葉台中学校。
1975年、もえぎ野の家。(2018年、リノベーションしてシェアハウス)
石田、幼稚園時代から青葉台に暮らし、
(1967年、すべてが真新しい街の周囲に里山があった)
ザリガニやカブトムシに夢中な小学生。
サッカーやったり、バンドやったり、の中高時代。
大学時代は、デキソコナイのシティボーイ。
その後、仕事では、子どもと自然にこだわったり、、、
なぜか、田んぼや畑。
2005年、『耕して育つ』
2023年、『でんえんとしさとやまっ子』
その間、
街の周囲にあった里山の名残りも消えていき、
子どもたちは、テクノロジーに囲まれてしまった。
(1984年、ジョージオーウエルが書いたようにはならなかったような、なったような)
(1985年、Windows、2007年、iPhone。2022年、チャットGPT)
だが、一方で、
最近、緑や農を求める人が増えている。ような、、、
そんな時代、を、も、感じている。
若き友人家族が、地方に移住して、
田畑に囲まれ、自分なりの農を目指し、ながら、
地域のコミュニティに受け入れられ(巻き込まれ)て、
「どうなるんだろう」、と、親心というかオジサン心で、心配もあるが、
そもそも、人生なんて、基本、「どうなるんだろう」なので、
ナンクルナイサー、かも、だ。
話がとぶ、ん、だけど、
その、田んぼから現代史を考える、と、、、
資料によると、稲作10アール(1反)の投下労働時間は、
(ザックリですが、、、)
1955年、220時間。
2020年、22時間。
なんと、半世紀の間に、10分の1に減っている。
単純に、「スゴイ!」
と、は、思うが、
労働時間が削減(効率化)されれば、「スゴイ」が、
それが、人の幸福にそのまま結びつくかは、、、???だ。
しかし、どうやって、それは、10分の1になったのか?
そう、(オオザッパですが、、、)俺なりに、考えると、、、
化学肥料、
耕耘機、田植え機、稲刈り機、
除草剤、
耕地整備、
コンバイン、
そして、いずれ、は、自動運転も、、、
そして、それらのテクノロジーによって、
百姓の、(いや食べる人たちの、も、)心も身体も変化した。
この心身の変化こそ、問題なのでは、と、思う。
農業、農、田んぼ、稲作、という視点で、
高度経済成長を考えてみようかと、
今、は、そんなことを、思っている。
(夏場に頭が働く自信がない:石田周一)