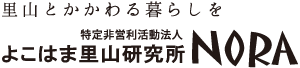第199回 うなわない
2025.3.30いしだのおじさんの田園都市生活
ずっと、トラクターに憧れていた。
(ずっと、は、30歳から45歳くらいまで、かな?)
トラクターが歩くと、畑の土が黒々とフカフカになる。
リセットされ、ステージができた、と、も、表現できるかもしれない。
種をまくにも、苗を植えるにも、ワクワクするステージだ。
トラクターで田んぼや畑を「耕す」ということは、そういうこと、のように思っていた。
耕耘機も、まぁ、同じ仕事をするのだが、
それをより効率的にカッコよく、やってのけるのがトラクター。
俺、35年ほど前から田畑で「農」をするようになった。
そして、そのころ関わった仲間たちは、「農」をすることを「耕す」と言っていた。
(市民が耕す農研究会、は、俺にとって決定的だったな)
しかし、15年くらい、トラクターのない耕作だった。
大小さまざまの耕耘機のお世話になっていた。
(最初にさかんに使っていた機械は、「ジェニー」と名付けていた。
分かるかい?ジューシーフルーツ、だよ)
いろいろと、失敗も苦労もしたけれど、
おかげで、耕耘機の扱いは、ちょっと自信あります、よ。
耕耘機は、日本で、1967(昭和42)年には300万台まで普及したが、
1955(昭和30)年には8万台しかなかった、そうだ。
1960年が、高度経済成長の始まりと言われるが、
そのころ、耕耘機のある家には嫁が来るとまで言われたそうだ。
(俺、1961年生まれ。父母は耕耘機とは関係ない生活)
(1967年は、俺が青葉台に来た年)
とにかく、いかにしっかり田畑を耕してステージを創るのか?
堆肥を盛って耕すことで土が豊かになると信じ、堆肥作りにも力を入れてきた。
そんな30年、以上。
しかし、実は、耕さないことにも憧れて、ずいぶん長い、のだよ。
『妙なる畑に立ちて』とか『わら一本の革命』に出会ったのは、
うん、これも、30年位前かな?
あと、実践書としては、徳野雅仁さんのイラストや写真の本もよく見ていた。
(徳野雅仁さんの実践は、もっと注目されてもいいように思う)
しかし、効率的な生産のためには、トラクターとマルチャーが必要。
広い農地で多くの野菜を生産するには、やっぱり機械の力。
それ以外の方法が思いつかないほど、そこに頼っている。
幸陽園農耕班の生産は、それが基本。
だが、自分の畑では、チガウやり方もチャレンジできるのでは、、、
と、思いつつ、
去年の5月のコラム188は、「やっぱ、うなっちゃった」。
以下、引用。
やっぱ、ビニールマルチの畝でしょ、植え付けや管理を考えたら。
そのためには、草や落ち葉が散らかった地面を耕してリセットしなければ。
そんな事情を優先させた土木作業となった。
実は、俺、けっこう土木作業が好きだったりする。
トラクターやマルチャーで風景が変わるのも、気持ち良く感じる。
「やっぱ、うなっちゃった」は、
できれば「耡う」はしたくなかったのに、
その後のもろもろを考えたら、「やっぱ」なのだった。
そう、リセットしてスタートしたのだ。
それを「好き」、と、ま、本心ですが、ヒラキナオッテいる。
だ、
が、
この春、
自分の畑ではトラクターは、使っていない。
耕耘機も、秋からは使っていない。
うなっていないのだ。
なので、先日も、ジャガイモの植え付けに、苦労した。
前作の通路だったところは、見るからに固い土、
そこを、耕さず、に、穴をあけて、植え付けた。
穴あけの道具をグリグリやって、を繰り返し、わき腹が筋肉痛になった。
そのとなりのブロッコリーを抜いたばかりの場所は、柔らかくてやりやすかった。
これが目指すところかな、と、思った。
つまり、機械で耕して土を柔らかくするのでなく、植物に耕してもらう。
やっと、「耕さない」の実践が始まった。
で、なぜ?「耕さない」なのか?
それが、土にとって、野菜にとって、いいというのは?
スピでなく、納得できるコトバがほしいので、、、
本を読む時間を作るには、努力が要るが、、、
金子信博『ミミズの農業改革』(みすず書房)
杉山修一『すごい畑のすごい土』(幻冬舎新書)
杉山修一『ここまでわかった自然栽培』(農文協)
吉田太郎『シンオーガニック』(農文協)
など、の、ページを開いたり、している。
いや、なにより、
明峯哲夫『有機農業・自然農法の技術』(コモンズ)だ。
(やっぱり書いた人を具体的に知っていると、チガウ、よね)
明峯さんの論を、俺の解釈で、勝手に、かなり乱暴だが、要約すると、
トラクターと化学肥料(どちらも化石燃料)を使う「効率的」な農業は、
今はいいかもしれないが、持続可能ではないことは明らかであり、
また、野菜という生命にも添えておらず、「生産」とは言えない。
地球全体から見ても、それは「消費」であり、自然に反する。
だから、それを食べる人間にとってもマイナス、、、
いや、すでに、その生命へのユガミは見えている。
こんなんで、いいですか?明峯さん?
こんなことをアレコレ考え、試し、作業する。
畑にいることが楽しい。
のだが、、、
それにしても、いつのまにやら、畑中心の生活。
四六時中野菜のことを考え、時間があれば畑に行っている日々。
基本、そこに幸せがある、と、感じている。
が、忙しい日々、
本も、しっかり読めてはいない。
本と畑は反比例してしまう、ようだ。
ツライ。
「百姓にガクモンは要らない」って、、、
ガクモンしていたら、百姓はできない、なのか?
ガクモン、って、ほどではないけど、
この原稿も、フラフラしながら、書きました。
ふぅ~、う~
うなわない、ことの、その意味を、いずれ書かないと、イカンな。
第300回までには、、、
(炎上商法には失敗、か? : 石田周一)