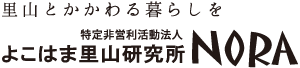第197回 一鉢会とGWEP
2025.1.31いしだのおじさんの田園都市生活
「一鉢会」というアイディア、
あの人、Kさんが言っていたことを思い出した。
30年も前のことだ。
例えば、
広い畑の一角に、トマトを10本、いや、20本か?もっとか?植え付ける。
その人は、その畑に足しげく通い、栽培管理に精を出す。
トマトは、栽培の難しい作物だが、それに挑戦できるヨロコビがある。
しかし、広い畑も作物も、その人のものではない。
その人は、個人では小さな家庭菜園をやっている。
愛好家だが、いわば、トーシロ。
だが、いや、だからこそ、より大きな畑に憧れがある。
農家さんみたいにトマトを作ってみたい。
自分で食べる数本というレベルではなく、
いいものをそれなりの量を作って、販売できるくらいのことをやってみたい。
トラクターに乗ってみたい、とか、刈り払い機で法面の草を刈りたい、とか。
そういう希望。
そして、その売り上げについては、自分の稼ぎにしたいわけではなく、
広い畑の主人公のものになればいい、と、思っている。
ボランティアだ。
ただ、たくさん植わっているトマトのうちの1本だけは、
自分のものということで、その収穫を持ち帰って、晩酌に添えたい。
それが、いや、それも?うん、モチベーション。
1本だけだから、「一鉢会」。
鉢植えじゃないんだけどね。
まぁ、「一本会」、とか、「一株会」というネーミングは味がないからかな。
で、もう一つのモチベーションは、
その畑の主人公たちの力になりたい!
だ。
その主人公たち、
彼らにはトマトやナスの栽培は、ちとハードルが高い。
畝間の草取りならば、なんとか、、、
それぞれのレベルで、取り組めるか?
雑草がカワイソウなくらいに徹底的やっつける子がいる。
自閉症スペクトラム障害の視覚優位と多動のなせる業。
だが、区別が分からずトマトも抜いちゃう勢いの子もいる。
黙々と作業しているかと思ったら、トマトをモグモグという子もいる。
そう、その畑の主人公は知的障害者と呼ばれる子たち。
(子といっても、基本18歳以上)
トマトのための堆肥作りの運び仕事ならば、得意!
栽培後の残渣の片付けも、とても得意!(ツクルより、コワスが好き)
みんな、個性豊かで、楽しい子たちだ。
そのボランティアKさんは、初期のグリーンを支えてくれた一人。
定年退職後に、家庭菜園を楽しみ、社会活動にかかわり、
そして、晩酌を愉しむ。
(あれ?どこかにいますね、そんな人。)
ご自分のお子さんが知的障害者であることも、グリーンを応援するモチベーションだ。
家庭菜園の経験からいろいろ教えてくれ、
グリーンの仲間たちをかわいがってくれ、
おもしろいアイディアをいろいろ披露してくれた。
その一つが、「一鉢会」というわけ。
グリーンで主人公である利用者さんたちが畑で活動するとき、
職員たちは、利用者さんのケアと農作物のケアを同時におこなわねばならない。
もちろん、利用者さんが第一だ。
グリーンの利用者さんは、指示をしておけば作業ができるレベルの子は、ほぼいない。
「重度」と言われたり、「強度行動障害」と言われたり、、、
常に、見守り、介入などのサポートが必要となる。
そんな利用者さんを気にかけていると、農作物のケアがおろそかになってしまう。
特に、細かい技術を要するトマト栽培などは取り組みにくい。
危険を伴うトラクター作業や刈り払い機作業も、安全管理に不安がある。
いっしょに地べたで草取りをするなどならば集中しやすい。
だから、広い畑でもいまひとつ生産が順調でないことも多い。
そんななかで、ボランティアさんは、農作物だけに集中してもらってかまわない。
むしろ、そうすることで職員だけではできないところを補ってもらえたら、
生産のレベルが上がり、お客さんに喜んでもらえるし、稼ぎも増える。
ボランティアさんの活躍は多方面。
いくらでも人手が欲しいということがイチバンかもしれないが、
今述べたような、作業への貢献はもちろんだが、
その方の社会経験、ビジネス経験などが役に立つこともある。
福祉現場の人間は、いわゆる一般的な社会経験が積みにくいということもある。
そこを補完してもらうのだ。
石田も、さる大手企業の幹部たちの訪問を受けたときに同席してもらったこともあった。
また、部外者の目が入ることで、閉鎖的になりがちな現場が緩むこともあり、
利用者だけでなく職員も含めて社会と繋がるいい機会になったりもする。
そして、もう一つ。
グリーンなどの障害者の事業所は土日休みの場合が多い。
農家は、(ツクル作物にもよるが)土日だからと休みはしない。
作物のことを考えたら、土日だろうが、必要な作業はある。
それを休むわけだから、作物に申し訳ないようなムズムズした感覚があった。
ドウシテモの苗物の水やりなどは、交替で休日出勤などもしていた。
そこで、石田は一時期GWEPという組織を立ち上げて活動していた。
土日に畑をやってみたい学生などを集めて、思い切り作業!
ウィークデイにやり残した作業や次週のダンドリの作業をする。
終わったら、(場合によっては作業中から)プシュッ、グビグビ、プハーッ!
GWEPはグリーン・ウィークエンド・プロジェクトなのだが、
ビールを飲んで、ゲゥエップをする、に、かけていた。
遅れに遅れたサツマイモの畝作りを手作業で頑張って、みんなで達成感の乾杯!
今も思い出す。(そのときのビール好きの学生ボランティアは今はベトナムで暮らしている)
な~に谷っ戸ん田をやっていたころ、石田は田畑の現場に立たない管理職だった。
週末のな~に谷っ戸ん田が、田畑を愉しんでリフレッシュする場だった。
そして、いずれは、な~に谷っ戸ん田とグリーンの活動を結び付けようと考えていた。
な~に谷っ戸ん田のGWEP化。
いろいろオモシロイこと!
妄想していた。
今も、妄想はいろいろ。
つづく、、、
(グリーンを退職したころのコラム、第34回あたり : 石田周一)