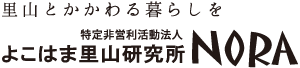第206回 田守俱楽部妄想
2025.10.31いしだのおじさんの田園都市生活
横浜で田んぼを守っていく方法の一つとして、
技術指導による人材育成と機械レンタルによる支援、
があるとよい、
のではないか、
と、
石田は考えている。
妄想している。
人材とは、
責任ある本気の耕作者。
結果を出してくれる人。
または、その候補者。
稲作の全過程をキッチリおこなうぞという人。
全く一人でというわけではなく、仲間と共同でもいいのだが、ちゃんとした代表責任者。
支援を受けながら、基本、1枚の田んぼを耕作する。
3畝(3アール、300㎡)から1反(10畝、10アール、1,000㎡)くらい。
米は2~8俵(120~480㎏)くらいとれる。
日本人の年平均消費量から見ると、2~8人分だ。
できた米については、支援を受けながら耕作したことを鑑みて、
基本的には販売はしないで、自家消費と知人へのプレゼントないし寄付。
と、機械のレンタル代金に充当。
それじゃあ小作人みたい?
うん、そうかもしれないが、それでもやろうという人!
(このへんは、ちゃんとした、積算も必要だが、それは、また)
田植えや稲刈りの「体験をしませんか?」とお誘いをすると多くの市民が集まる。
その中から、本格的に耕作をして米を作りませんか?
支援もあるけど、責任もありますよ。
と、お誘いをした場合、どれくらいの人が応募してくれるだろうか?
興味を示してくれた人がいたとしても、
「空いている田んぼはあるから、はい、どうぞ」では、とうてい無理だ。
一方で、
稲作をするのにどんなものが必要になるか、
全く分かっていないのに「やりたい!」と、
「思い」だけで出発してしまう人もけっこういたりする。
実は、石田自身がまさしくそうだったのだ。
20代の半ばを少し過ぎたころ、
「田んぼをやる」と突き進んだ時の石田は、何も分かっていなかった。
稲作を全うするには、
それなりの技術と、どうしたって機械が必要だ。
もちろん、時間と体力と人手いう労力も必要。
そこで、労力を約束できる人に技術指導と機械のレンタルで支援する。
技術指導は、
作業計画と作業方法。
座学と実地指導。
いわゆる体験でおこなう田植えと稲刈りは米作りのハイライトだが、
それを支える様々な工程での細かな作業によって稲作はなりたっている。
田起こし。畔切り。荒代掻き。畔寄せ。畔塗り。肥料まき。本代掻き。
泥と汗にまみれて、そして、やっと、田植え。
その間に、水管理や草刈りを適宜適切におこなう。
田植え後も、暑さの中で、水管理、(農薬散布)、草刈り、草取りなどなど。
そして、4ヶ月ほど、稲の生長を見守り、稲刈り。
天日干ししたら、脱穀をし、籾摺り、精米。
種籾だったものが、苗になり、稲に育ち、米になる。
これらの一つ一つは、書物やネットで身に着けるのは難しい。
というか無理。
インストラクターによる実地の技術指導が必要。
いい指導があっても、それでも、そう簡単には身につかないと思った方がいい。
そして、この過程を支える機械。
これは、ここでは、基本、大きな農家が使う最新式のものではなく、
昭和のころのタイプを使うことを想定している。
今では、田起こしや代掻きには大型トラクターがあるし、
なんだったら、畔切りや畔塗りも機械があるのだが、
手押しの耕耘機と手作業で、えっちらおっちら田んぼを作る。
田植えも乗用の田植え機ではなく、歩行型の田植え機と手作業。
稲刈りも、最新式のアッという間に刈り取りと脱穀をするコンバインではなく、
歩行型のバインダーと手作業。
天日干しをしてハーベスター(脱穀機)で収穫。
なんなら、足踏み脱穀機と唐箕。
ここで列挙した機械を自分で所有し管理するのは大変だ。
うまく中古でそろえたとしても、ざっと200万円はするだろう。
置き場所にも困る。
今どきの小さな家の1軒分の30坪くらいは必要だろう。
田植え機、稲刈り機、脱穀機などは、田んぼが1反なら年間で半日か1日の稼働。
364日は保管というものだ。
これをレンタルできる体制を作ることが支援として重要。
もちろん使い方を技術指導するのだが、1年に1回のことだから、
そう、簡単には身につかないわけだ。
機械の置き場所があって所有している農家さんでも、
これらのどれかが壊れたら、「もう田んぼはやめようか」となるパターンが多い。
どの機械も1反の田んぼの米の売り上げ(収益ではない)の5年分くらいはするし、
それこそ、1反の田んぼを作っていても収益は上がらない。
だから、機械を共同所有する意味もある。
この企画でプレイヤーになる人は、収益目的では成立しない。
本格的に稲作をするのだが、
それは、自分や家族友人の食べる程度の米を作り、
その過程を楽しんで、自給することにヨロコビを見出し、
責任をもって田んぼを耕作することで、水田の保全に貢献する。
その貢献を約束することで、技術指導と機械のレンタルの支援が受けられる。
そんな仕組みを創り、
少しずつでも仲間を増やしていければ、
と、石田は妄想しているわけだ。
田んぼを守る「田守倶楽部」。
(以前にもこんなことを書いたような記憶が、、、曖昧な、、、石田周一)
次も同じようなことを書きますよ。