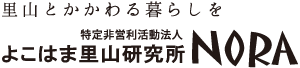第104回 宝塚レビュー?!セグロアシナガも背けた羽を背負う虫の正体は?
2025.10.1映像の持つ力
うわぁ。稲の穂が垂れている。
田んぼの遠景はなんと美しいことか。
9月中旬の緑米を最後に6種全ての穂が出揃いました。
紅、紫、緑、黄。穂の登熟に合わせ、品種ごとに色の違いがくっきり現れます。
田んぼに入り観察です。
稲の草姿も、品種ごとに特徴があり成長が違います。いくら歩いても飽きません。
同じ品種でも、稲の穂一本ごと、穂のなかの籾ひと粒つづ、成長が違います。
茎の中で大きくなった幼穂が穂を出す穂ばらみ期の動きはダイナミック。
一本の穂の中には60-100粒ほどの籾が入っています。
幼穂が茎から出るとき、連なっているお米一粒ごとに、動きの違いが大きく出ます。
ああ、連なっているけれど、このお米の一粒づつは別の命である。
当たり前だけど、その当たり前のことにはっとします。
観察はノラ仕事の中で静かな動きです。だかしかし、目にするものは原初的でダイナミック。
一粒のお米が成長する素朴さは、個の命と連なる全体が成すうねりそのもの。
稲刈りまであと数ヶ月。
水枯れと台風をしのぎ、今年のお米の出来はどうでしょうか?
神丹穂、チベット黒米、紅染、朝日・初霜、緑米の順に稲の穂が垂れています。
去年はイネカメムシの大量発生で食べることはおろかタネが継げるか肝を冷やしました。今年はイネカメムシはほとんどいません。
通算16年、新しい田んぼでのお米づくりは3年目。いよいよ美味しいお米が食べられます。
小さな森のある畑は、今日も生きものが賑やか
8月下旬になると、ナツメの木の枝の至るところに、宝塚のレビューの羽を背負う虫がびっしり付いています。振り払っても、減る気配なし。触れると即ピョンと飛んでしまうから捕獲もできない。
この虫、初めて観察したのは去年かしら。果樹に白いフリルのような羽を持つものが動いており、まさか・・、よくみたらやはり虫です。
白い羽をまとう姿は宝塚のレビューを連想させます。正体は何?チュウゴクアミガザハゴロモと呼ばれる幼虫のようです。
(この時は華やかな形態のムシがいるもんだと微笑ましくさえ思いました。)
ナツメには、スズメバチ、アシナガバチもどんどん訪れています。さて、大量発生しているチュウゴクアミガザハゴロモをカメムシ同様に捕食するのか?。
アシナガバチがチュウゴクアミガザハゴロモに近づきました。え、羽の部分に触れたのか、アシナガバチは瞬時に顔を背け、捕食おろか飛び去るではないですか。
なんとアシナガバチが捕食しないとは・・大変だ。
予想通り、チュウゴクアミガザハゴロモは向かうところ捕食者なし?、あれよという間に、果樹だけでなく、オクラその他にも生息域を増やしています。
オクラが花芽をつける茎には幼虫と成虫がたむろしています。
うちは葉取られリンゴ
昨年までの収穫は数個だった姫リンゴ。今年は2kgも採れました。
収穫量もさながら、色も立派に赤々とした姫リンゴ色です。
一般的なリンゴの栽培は見た目の色をよくするために収穫の前に葉を摘み取ります。
うちは、果樹を次から次へと渡り進む、毛虫(シャチホコガの幼虫)がし、きれいに葉を取り、自然な葉取られリンゴとなりました。
同じ豆なのに・・この違いは?
奈川ササゲが強い。水枯れで萎えている小豆を尻目に葉の勢いよく非常に元気。
8月末には着花を確認。3日後には鞘が伸びはじめています。
調べるとササゲはアフリカ原産。乾燥に強いわけです。
土壌が良くなりすぎて、豆が育たない?
小さな森のある畑を中心に、土質や広さ環境の違う3箇所で、自然農風(不耕起、肥料なし、農薬なし、草マルチ、天水、動力機械なし)の畑をしています。
17年目に入る小さな森のある畑ではここ数年、変化が起きています。大豆や小豆の鞘(サヤ)の付きが少なくなりました。
対して3年目になる畑は小豆や大豆の鞘が丸々と育ちます。
原因は土壌が肥えたせいでした!
証拠に、小さな森のある畑では、糸ミミズほどに細かったミミズが今では小指の大きさです。対して3年目になる畑は、長年に渡り耕運だけ行われた畑です。ミミズも細くまばら。
なんとも面白い。土壌生物の変化は地上で育つ作物の変化で可視化されるのですから。
幻の果物ポポー、今年も豊作です
ここ数年、酷暑の影響で、ポポーは秋を待たずに全て収穫。
毎日、ポポー拾いをすることで、落下し食害にあう数は減り、パパイア・マンゴー・バナナがバランスよく配合された食味のポポーを収穫することができました。
(中川美帆)