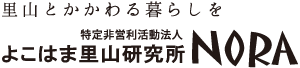第102回 セミが激増。抜け殻があちこち。産卵ラッシュも!
2025.8.1映像の持つ力
“今日の畑は、いたるところで、クモの巣が雨の雫でくっきり見えて、キラキラしてました。
雨の雫が、整列して風に揺られる様子は、まるでウィーンで見た、クリスマスのイルミネーションのようでした。”
そう、お便りしてから3週間。まとまった雨は無し。(2025 7/30現在)
この様子だと、雨あがりにコガネグモ科のクモがつくる、足もとの草から見上げた果樹の合間など、至るところで畑を涼しげに飾る、小さな小さな電飾は見納めかしら。
今年は、セミが驚くほど増えています。抜け殻が樹下を中心にあちこちに残され減りません。
7月3日ニイニイゼミの抜け殻を観察。
2日後には、ジィッと鳴き声が聞こえたと思ったら、羽音が近づき私の帽子に追突。
もしかして・・?? はい、今年初のニイニイゼミを帽子のつばごしに観察しました。
先方からお越しくださるとは!なんとも感慨深いです。
さらに、続きが。
ニイニイゼミの抜け殻を観察した4週間後、産卵ラッシュに遭遇しました。
私たち人とは成熟の速さが違いますね。
いま世界中で、昆虫の数が減っていること、生態系への影響、その深刻さが認識されています。
その中で、うちの“小さな森のある畑”は、ありがたいことに昆虫や土壌生物が増えていることを確認出来ます。
田んぼでは、うちの稲の上空をトンボが群れてヒュンヒュン、スイスイと乱舞しています。
トンボが個々で動いていながら、それでいて群れで同調した動きもあるし、見飽きません。
上空から田に視線を戻すと、ふわっーとアオイトトンボが交尾しながら横切ります。
富士山が見える、この田んぼ地帯は、サギ、カモ、ツバメやトンボ、カラス、スズメ、カエル、バッタ・・・と、それぞれ違う飛行力に魅せられるばかりです。
田植えを始めた6月末から、夫と2人で日の出を合図に、朝飯前で出勤前のノラ仕事を続けています。
雨は無く酷暑日続きですから、しんどいけれど、それ以上に、毎日、田畑を観察できる事の幸運に気づかされます。
生き物それぞれの季節行動、生き物ごとに持つ生態の変化、その賑やかな命のひとつながりに出会い、同席できる時間は得難いものがあります。
今年の田んぼは新しい試みをいくつか行いました。
田植えは、ありがたいことに、仮説を立てたアメリカザリガニ対策が功を奏し、植えたそばからハサミで稲をチョッキン切られまくることは防げました。(ほっ)
残す懸念はイネカメムシ。どうなる?
田の配水日。夫がわたしに手を振ります。“水路から田の水口に向けて水の流れが起きる瞬間を見たよー”。
ワオ。今年は田の入排水経路を変える実験を始めました。
・4月にせっせと畦の幅や高さを変える
・ビオトープを区画割り
・田んぼ内の水路を増設。
実際に、給水が始まってからは、水の流れを確認し微調整。水口の開閉タイミングを変更し、新しく排水口を設けたり。
増設した田んぼ内の水路は、中干しで水が渇れる期間、生き物の避難場所になりました。
水田は生きもののゆりかご。
主食のお米を作ることが、生物多様性を支えてもいる。
田んぼは人類史上最大の発明の一つだとか?。
規模に関わらず、ノラ仕事のある暮らしは、先人がわたし達にのこした生物多様性を繋ぎとめる道すじにあります。
なんてったって人も自然の一部。
(中川美帆)