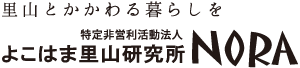第130回 宇野常寛『庭の話』
2025.8.1雨の日も里山三昧
- 宇野常寛『庭の話』(2024年、講談社)
南房総で地域づくりに関わっている人たちが開いているオンライン読書会に参加し始めて、ちょうど5年が経過した。
最近は、本を読む量がめっきり減っているので、この読書会で取りあげる本を読むことは、最低限の読書時間を保つのに役立っている。
本書は、この読書会のために読み通した。
庭の話といっても、植物や環境の話ではない。
著者の説明によれば、情報社会論になるようだ。
参照されるのは、真木悠介(見田宗介)、リチャード・ドーキンス、ジル・クレマン、エマ・マリス、ヤーコブ・フォン・ユクスキュル、鞍田崇、井庭崇、クリストファー・アレグザンダー、國分功一郎、柄谷行人、藤原辰史、坂口安吾、丸山眞男、糸井重里、ハンナ・アーレントなど。
本書を貫く問題意識として、格差の問題がある。
もちろん、今日の格差問題に迫る際には、資本家と労働者の階級格差に注目するだけでは十分ではない。
かつて、多くの人びとは歴史=物語を生きる中が、自らのアイデンティティを確認していた。
しかし、21世紀の今日においては、社会をゲームとして把握する。
そして、グローバルに広がるひとつの巨大なゲームには、世界中のプレイヤーが参加しているが、それは大きく二層に分かれる。
デイヴィッド・グッドハートという英国のジャーナリストは、これをAnywhereな人びととSomewhereな人びととして表現している。
典型的な姿をわかりやすく表現すると、Anywhereな人びととは、今日のグローバルな情報産業や金融業のプレイヤーであり、自身の仕事を通して「社会」(グローバル市場)に関わることができる。
一方、Somewhereな人びとは、製造業を中心とした旧い産業に従事しており、国民国家の一員としての自意識を持つ旧先進国の中産階級。南北格差によって富を得てきたが、排外主義的傾向を帯びやすい人びと。すなわち、Anywhereな人びととは世界中のどこでも生きていける人びとのことで、個人の力でグローバルな資本主義というゲームをプレイする。
対して、Somewhereな人びとはローカルな相互評価のゲームをプレイし、その中でコスパ良く強い承認を得られるのが、他者への感情移入を原動力とするSNSを通した政治参加であるという。
先月の参議院選挙の結果は、このような格差が影響しているのかもしれない。
さらに、ここで重要なことは、Somewhereな人びとSNSを通した相互評価のゲームに熱狂すればするほど、Anywhereな人びとは収益を上げるプラットフォームを作り上げていることだ。
このような構造から抜け出すにはどうすればよいのか。
そこで、著者が持ち出すのは「庭」である。
キャッチフレーズは、プラットフォームから庭へ。
著者が庭に注目を促すのは、そこが植物など人間以外の事物にあふれている一方で、同時に人間の手によって切り出された場所であるからだ。
そのように視線を誘導してからは、人間と自然の関係について述べられている。
エマ・マリス『「自然」という幻想』や、岸由二さんの小網代の森の保全活動などにもふれられている。
自然を人間から切り離して自然を守ろうした旧来の保護思想とは異なる里山的な、あるいは多自然ガーデニング的な「自然保護」以降の関わり方について肯定的に書かれている(→福永真弓・松村正治編『答えのない人と自然のあいだ:「自然保護」以降の環境社会学』)
こうした事例紹介を織り交ぜながら、著者は「人間と人間とのコミュニケーションを相対化し、人間と人間外の事物とのコミュニケーションを豊かなものにすることが求められる」と語る。
この主張は、里山保全に関わってきた者からすると、深く肯くことができる。
その後、現代の「庭」が備える条件を、一つひとつ議論しながら加えていく。
その3つの庭の条件とは次のとおり。
1)人間が人間外の事物とのコミュニケーションをとるための場
2)人間外の事物同士がコミュニケーションをとり、外部に開かれた生態系を構築
3)人間がその生態系に関与できるが、完全に支配することはできない
この条件が満たされるように、庭師として次のとおりに介入する。
すなわち、①人間外の事物たちの生態系をデザイン→②その事物たちと人間の関係をデザイン→③その結果として発生する人間間のコミュニケーションをデザイン
このようにデザインされている例として、武蔵小金井の「ムジナの庭」が紹介される。
ここは、庭で採れる植物や、廃棄される素材を使ったエシカルなものづくりを中心におこなっている就労継続支援B型事業所である。
この「庭」では、メンバーさんが自分の独自性を保ちながら全体にかかわっていて、無理に全体の動きに従わされていない状態が実現されているという。
このような集合体を、サルトルにならって「コレクティフ」と呼び、共通の目的を持つグループと対比させる。
このあたりの議論は、NORAの組織運営で大事にしてきたところで、基本的な考え方には賛同する。
このあと、民芸運動やパターン・ランゲージの議論を挟んで、自らが提唱した「遅いインターネット」論を更新する必要性を説く。
つまり、相互評価のゲームに参加しない(=遅い)ことを提案したものの、事物を創造していくこと、制作していくための動機付けが足りていなかった。
そうした欲望を引き出す環境の構築が必要だという。
私は、都市近郊に暮らす人びとに里山と関わることを勧めているが、それは都市のライフスタイルに自然のリズムや循環の仕組みを取り入れると、世界の見え方が変わってくるからである。
私たち人間の「社会」よりも、人も自然も含めた「世界」の方がはるかに広く大きいので、「社会」に息苦しさを感じていたとしても「世界」の中で生きていると感じられると、楽になったり気持ちよさを感じたりすることが少なくないと思っている。
さて、本書は次第に、実態のある庭の話から離れていく。
著者の関心は、あくまでも高度に情報化された社会に振り回されずに、自分を自由に生きるための処方箋なのだ。
ここで社会の中で浮遊し、ときに集合的に熱狂して、あらぬ方向へ社会を動かしてしまう個人に対して、これまでは右派も左派も、共同体への回帰を提案しがちであったが、著者はその道を拒絶する。
人はときに孤独でもあるべきと述べ、共同体主義者が持ち出すコモンズではなく、また、プラットフォームでもなく、「庭」が必要だという。
その後、坂口安吾の小説『戦争と一人の女』を参照しながら、著者は自ら理念的に掲げる「庭」について、そこで人間が一時的にだが「何ものでもない」存在に変えることができる場所だと説明する。
この部分は「居場所」の議論とも近いけれど、「庭」では世界は自己と無関係に変化すると感じさせるという条件も加わっている。
「庭」では、世界にコミットするという手触りを感じられる一方で、世界はただ変化し続けているとも感じられるという感覚は、家庭菜園や里山づくりに関わっていると、よく理解できる。
結論部では、「庭の条件」ではなく、「庭」が大きな力を発揮するための「人間の条件」が検討される。
「人間の条件」という言葉からわかるように、ここでは、アーレントが整理した人間活動の3つのカテゴリー「労働labor」「制作work」「行為action」に依拠して議論が進む。
初期のインターネットとそのオープンソースの文化において、ユーザーが共同でソフトウェアやプラットフォームを開発し、改善していく過程があった。
このようなプロセスが「行為」、政治の場でも展開されるならば、民主主義はもっと良くなると多くの人が期待していた。
しかし、実際は情報化の進展によって、民主主義の空洞化が進んだ。
先月の参議院選挙の結果は、その事態の深刻さをまざまざと見せつけた。
著者は、著者は、デモは意識の高すぎる「市民」を、選挙は低すぎる「大衆」を非日常に「動員」するシステムだと喝破する。
私たちには、等身大の人間として、日常的に社会をつくる仕組みが必要である。
著者は、vTaiwan(v台湾)などのクラウドロー(インターネットによって市民が法律や条令などの公的なルールの設定に参加するサービス群)を例に挙げ、人びとがそれぞれの専門的な知見を生かし政治に関与することを提案する。
そして、「非日常に動員された市民/大衆のポピュリズムから、日常を生きる職業人の手に政治を取り戻すのだ」と訴える。
こうした人間側のアップデートによって、プラットフォームの影響から相対的に自律できる(弱い自立)「庭」もまた機能するはずだと結論づける。
以上、ときおり自分のコメントも加えながら、本書をふりかえってみた。
全体的な構成は、しっかりしているとは言えない。
著者の明確な問題意識を携えて、いろいろな議論を批判的に参照し、いくつかの実践例を紹介しながら、ああでもないこうでもないと話を進めていく。
最後の方で、慌ただしく結論へと議論がなだれ込んでいったのは、どこかで打ち切らないと、終わらないと思ったからなのだろうか。
これが専門書であれば突っ込みたくなるところも多かったけれど、そのような本ではない。
読み通してみると、著者の思索の旅に同行できたような満足感は残った。
今日の民主主義の危機について考えるためには、大事な視点を得られるし、さまざまなヒントも得られるはずだ。
全体的には好印象だったのだが、2つほど不満を述べておきたい。
一つは、「庭の話」というタイトルであり、人間以外の事物の重要性を指摘しているけれど、植物、生きものとのコミュニケーションがもたらす豊穣な世界が、あまり描かれていない。
これは、著者にそうした経験が少ないからかもしれないのだが、着眼点はとても優れているので、もっとその世界に踏み込み、自らの経験を通して自説を展開されたら、もっと私好みの議論になったように思う。
もう一つは、現代の情報社会において、Somewhereな人びとが取り残されていることに着目することは重要であるが、その問題性がAnywhereな人びとの視点からのみ語られているように感じられることだ。
このリアリティも足りていない。
まとめると、自然や社会について主張しているけれど、両者ともに距離感があって、議論がやや空回りしているように感じられる部分があった。
もっとも、このように私が難点だと感じるところは、私が取り組むべきところであって、著者の持ち味が発揮できるところではないだろう。
本書を読んで、私が何を考えるべきなのかが、より明瞭になったように思う。
その点、著者の宇野さんには、深く感謝したい。
(松村正治)