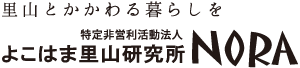寄り道73 構えないでいられるコミュニティとのフラットな関係
2025.4.1雨の日も里山三昧
2020年代初め、新型コロナウイルス感染症が拡大し、人びとはステイホームやリモートワークを体験した。その後、コロナ以前の仕事や暮らしが戻ってきたが、コロナ禍をきっかけに移住や二拠点居住を始めたり、社会的起業に踏み出した人びともいた。私はそうした動向に関心を持ち、都心から2時間ほどの距離にある千葉県南房総エリアと神奈川県県西エリアで移住者や二拠点居住者を中心に話を聞いた。彼(女)らは、大学を卒業後にいくつかの仕事を経験し、生き方を模索するうちにコミュニティや自然との関係を考えるようになり、現在に至っていた。
以下に5人のライフヒストリーを紹介し、現代社会におけるコミュニティや自然の意味について考えるヒントを得たい。
Aさん(40代後半、男性)は、南房総市内で築300年の古民家を拠点に、面積3,000坪の里山をシェアするプロジェクトの代表を務めている。2015年に始動したこのプロジェクトでは、都内在住者をターゲットに「いきつけの田舎をつくろう」と呼びかけて賛同者を集め、20年間放置されていた古民家を改修し、荒れていた裏山に手を入れ、休耕地を活用したりしてきた。
Aさんが南房総地域に関わるようになったのは2007年で、東京で会社員として忙しく働いていたときに「週末のエスケープ拠点」として館山にアパートを借り、二拠点居住を始めたときにさかのぼる。その後、南房総で仲間4人と一軒家をシェアし、東京ではシェアオフィスを運営するなどの経験を積んだ。2015年、古民家付きの里山を借り受けて「シェア里山」のプロジェクトを始動し、ほぼ同時に近くの一軒家へ移住した。生活の比重を南房総に移すと会社を設立し、以前からおこなっていたウェブ制作のほかに、自治体の地方創生事業に携わるようになった。
Aさんが始めた「シェア里山」では、メンバーになると、毎月2回週末におこなわれる定例活動に参加できるほか、リアルな交流イベントやオンラインのコミュニティに参加できるなどの特典がある。月例活動では、「小屋を建てよう」「竹の活用を考えよう」「自分たちで醤油をつくろう」など、メンバーが取り組みたいことに挑戦できる場を提供している。里山の衣食住にまつわる多様な活動が、実践を通したコミュニティづくりの機会となっている。この里山は、シェアメンバーのサードブレイスであるとともに、Aさんにとってもそのような場となっている。自分で制御しようとはせず、「変化ありきで楽しむ感覚」を持ちながらフラットな関係性を大事にしてきた結果、メンバーは段階的に入れ替わりながら続いている。
Aさんは、生活拠点を南房総に移したとき、「アウェイの面白さ」を感じたという。よそ者としての疎外感を覚えるよりも、文化の違いを楽しめる感性が興味深い。無理をして地域になじもうとするわけでも、あえて距離を取ろうとするわけでもなく、必要なときに必要なかたちで関わるスタンスを採っている。たとえば、地区の水路清掃に合わせて月例の活動日を設け、多くのシェアメンバーが参加することで、地区にとっては共同作業への参加者が増えて作業がはかどるし、メンバーにとっては得がたい体験の機会となる。
これまでのコミュニティ論では、地付きの住民と来住者・来訪者との関係に関心が集まり、両者の緊張関係をベースにして語られてきたように思われる。しかし、ここでは、地付き住民との関係に気を配ることよりも、シェア里山を必要としている人びととつながり、人びとをつなげて緩やかなコミュニティをつくることに注力してきた。
私は、Aさんが中心になって月に1-2回のペースで開催されているオンライン読書会に、コロナ禍に知り合いに誘われて参加するようになった。読書会では、テキストを正確に読むことが目的ではなく、読んでどう感じ考えたのかについて、それぞれの意見や感想を交換することに重きを置いている。Aさんは、リアルかオンラインか、東京か地方かなど、二項対立的な論点が立てられると、どちらかの立場に与するのではなく、その2つの考え方の良いところを生かそうとする。どちらが正しいのかという議論を進めるのではなく、どうすればうまく現実的に「ハイブリッド」できるのかという視点から発言されるのが印象的だ。
あるイベントで、Aさんが次のように自らのコミュニティ観を語るときがあった。すなわち、「コミュニティっていうと、古くはオウム真理教とかの影響もあって、コミューンとか怖いって思う人もいるんですけども、若い世代はコミュニティっていうのがすごくポジティブなものになってるなと思っていて、いま高齢化している里山のコミュニティに新しい流れができるんじゃないかなと思っています」。この言葉には、地域の課題解決には人的資源としての人的資源が必要であり、そのために地縁型であろうとテーマ型であろうと人のつながりを「コミュニティ」と呼んで積極的に生かそうとする姿勢が込められている。Aさんは、現代の里山が担い手不足で課題山積だとされる見方を反転させ、クリエイティブな発想の起点や魅力的な資源を見いだせる「余白」が広い空間として、新たな価値と可能性を地域に創出しているといえよう
つぎに、「シェア里山」のメンバーのひとりで、2022年に都内から南房総地域の館山市へ移住したBさん(40代半ば、女性)を紹介しよう。Bさんは東京の大学を卒業後、京都で7年、転職して東京で約10年働いてから独立し、現在は人材育成のコンサルタントやライター、他会社の下請けでプロジェクトマネジメントなどをおこなっている。南房総エリアに関心を持ったのは、都内でルームシェアしていた同居人がマンションを購入するからと出て行くことになり、自分は会社員ではないから二拠点居住もいいかなと思っていたタイミングで「南房総二拠点大学」というイベントに参加したことがきっかけだった。日帰りすることができて都内にも通える距離だと実感したほか、このイベントでAさんとつながり、「シェア里山」というコンセプトに共感し、シェアメンバーに加わることにした。なかなか月例アクティビティに参加できずにいるうちにコロナ禍に入り、ますます現地へ行くことができなくなる一方で、リモートワークの時間が増えたことで、都内に住む必要はないかもしれない、まずは数日間滞在してみようと思って館山に来てみた。すると、何気なく眺めていた不動産情報で良いアパートを見つけ、自宅の賃貸の更新時期でもあったので、普通の引っ越し感覚で行ってみてダメだったら戻ろうかなという気持ちで2022年に移住した。
Bさんは、移住後も仕事をあまり変えておらず、週に2日程度は打合せなどのために都内へ出かける。東京も魅力的だと思っており、月に1回も行かなくなったら、仕事をする上での感度が鈍るかもしれないと考えている、東京との間の片道約2時間のバス移動は慣れてしまえば意外と楽で、交通費はかかるけれども、それも必要経費として自分で上限を決め、その範囲であれば構わないと納得している。
Bさんは「自分で田舎暮らしをやりたいというよりも、体験はしたいしけれど自分では無理と思っている」から、「シェア里山」という関わり方は好都合であった。さらに、シェアメンバーのコミュニティの縁で移住してみたら、そのコミュニティ周辺の人から地域内で開かれる小さなイベントや会合に誘ってもらえる機会が増えた。地域の人から「こっちにいる人」と認識されるようになって新たにできたことや出会えた人のことを思うと、二拠点居住ではなく移住を選択して総じて良かったと感じている。また、独身なので老後のことを心配して将来を考えることもあるが、老人ホームに入るときでも南房総エリアはいいなと感じており、長く住めたらいいなと思うようになったという。
Bさんの場合、これまでも新興国に向けたソーシャルファイナンスに取り組む団体にプロボノとして関わるなど、自分の時間を趣味以外に社会的な関心にも向けて使ってきた。そのなかで、本業の仕事と違うことができるから面白いと思う人がつくる関係性に居心地の良さを感じてきた。いくつものコミュニティに関わってきた経験から、「共通しているのは、ある種の自由さと適当さがある集団っていう辺りはいいな」と考えている。「ガチな田舎暮らしがしたいという色が強いと私は引いちゃう」と言うBさんは、自分のようなノリで移住生活をしていることを気軽に言える場所があれば、移住や二拠点居住を構えずに始められる人が増えるのではないかという感触を抱いている。
今度は、神奈川県県西エリアの南足柄市にコロナ禍の2021年に移住したCさん(40代前半、男性)を取りあげる。Cさんは西アフリカで国際協力分野の仕事に従事し、帰国後は横浜市内に住み、組織開発や人材育成のコンサル会社に勤めていた。コロナ禍で完全にテレワークとなったとき、当時住んでいた横浜市内の社宅は子どもたちがいると仕事ができる環境ではなかったので、広いところへ引っ越そうと思い、都心まで通える範囲で物件を探すうちに南足柄の田園風景に惹かれて移住した。
Cさんは、移住して間もない2022年、林業の6次産業化によるまちづくりを目ざして南足柄市と民間企業が共同で設立した株式会社の代表に迎え入れられた。しかし、地域の課題は林業の周辺だけで解決することは難しいと感じ、会社を辞めて新たに非営利株式会社を2024年に創業した。地域の課題をみんなで解決するためには、一般的な株主の利益を優先する法人ではなく、所有者を株主に限定しない法人の方がよいと考えて非営利株式会社を選んだのであった。
Cさんが辞めた会社で共同代表のひとりを務めているのがDさん(20代後半、男性)である。Dさんは、大学までは東海地方で過ごし、東京の会社に就職した2020年に横浜市内へ引っ越した。最初に就職した会社を辞めてしばらくは、全国を転々とフィールドワークをしながら多拠点居住のかたちで暮らしていた。ここでいうフィールドワークとは、「SDGs先進地域というか、次の時代に必要かなっていう要素を自分でチェックしたところを周りながら、話を聞きながら、手伝いながらということ」を意味する。
Dさんは、多拠点居住暮らしの一環で、小田原市内の休耕地を生かしたソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の事例を視察したことが契機となり、神奈川県の県西エリアでいろいろなプロジェクトに関わることになった。また、仲間たちと湯河原町内の古民家を改修して地域の拠点を立ち上げ、そこに住み込んでゲストハウスのようにして運営していたこともあった。その後、この拠点事業はやめることになって住む場所を探していると、ゲストハウスの宿泊客だった人が南足柄に移住することになり、その人から空いている古民家を紹介された。全国を巡るうちに森林に関わる仕事に就きたいという気持ちが膨らんでいたこともあり、先に移住していたCさんの動きにも興味があったので、2023年に南足柄へ移住したという。
Dさんは、自らが共同代表を務める南足柄の会社のほか、千葉県内の再生可能エネルギー事業をおこなう会社の仕事も担い、さらに県西エリアに関わるきっかけとなった小田原の会社の事業も引き受けるなど、複業によって生計を立てている。持続可能な地域づくりという感覚で仕事をしており、個人的に課題だと思っていることを研究しながら生きている側面もあるという。
一方でDさんはCさんらとともに、地域の課題を題材にした企業研修や都市部の人を集めてスタディツアーを企画・運営する側に回ることもある。あえて南足柄まで足を運ぶ人びとは、「だいたい面白い方々というか、自分の考えや価値観を持っていたりする方が多くて、面白い出会いが多くある」とふりかえり、この場所へ移住して良かった点だと考えている。
Eさん(40代前半、男性)は、移住者・二拠点居住者ではないが、南足柄に何度かフィールドワークで訪ねた後、2024年に社会的起業家となった。ここに至るまでの人生をふりかえると、「純粋に思っていたことが途中で薄れてきて、それがまた現れてきたみたいな印象」だという。
Eさんは、子どもの頃から地球環境問題に関心があり、大量消費・大量廃棄の社会ではいけないと考えるなど、社会に良いことを仕事にしたいという純粋な気持ちを持っていた。大学では、環境経済学を学ぶために経済学部を選び、また、環境問題と経済成長の両立を考える文化系のサークルに入り、NPOを通して短期の海外ボランティア活動に参加したこともあった。一方、学生時代には、環境というキーワードとともにビジネスにも関心を持つようになり、地域通貨を導入して地域の活性化を図るまちづくりのプロジェクトに関わることもあった。しかし、いざ働くとなったときには、自分で何をやりたいのかわからなかったので、名の知れた会社に就職するという周りの流れに乗って、大阪市内のメーカーに就職した。
就職先では、社会や環境には無関係の泥くさい仕事で、営業部門のシステム企画の仕事を任された。しかし、営業の現場は軍隊式のようなところがあり、厳しいノルマで心が病んでしまう人も数多く見てきた。次第に、自分の仕事は何のためのやっているのかと疑問に思うようになり、十数年間働いて辞めることにした。その後、これまでと社風の異なるところで働こうと思い、東京のスタートアップ企業に転職したが、IPO(新規公開株式)をめぐり社内が混乱していたので半年でまた転職することにした。その転職先は、技術力を生かして社会に必要なものを開発すれば役に立つと信じていたが、元投資家の社長が企業価値をどう高められるのかを考えIPOを目ざしていた点は前の会社と変わらなかった。Eさんは人を道具のように使う社長の言動にもやもやしながらも、上場して会社が大きくなれば海外展開する可能性もあると6年半働き続けたが、その会社は倒産した。
会社の資金繰りがいよいよ厳しくなった頃、Eさんは資本主義の世界に染まっていたことを自省し、「共感資本社会の実現を目ざす」非営利株式会社の人材育成プログラムに参加した。このプログラムの基礎コースは、共感を基礎(資本)に活動できる社会を実現するためには、社会関係資本の増大が重要で、人と人とがつながり、人間としての成長が促される必要があるという考えにもとづき、約3か月にわたって多様な実践者の講義を聞き、議論するという内容である。基礎コースの卒業生を対象とした実践コースには、宿泊を伴うフィールドワークが用意されており、Eさんはこれに参加するかたちで南足柄に通った。
この人材育成プログラムを通して、今日の社会のレールに乗らずに生きている多くの人びとと出会い、いろいろな生き方があることを知り、枠に囚われなくてよいと思えたという。たとえば、南足柄に移住したCさんが、いま地域を盛り上げる活動を進めていることから刺激を受けた。気負うことなく、ただそうしたいからそう生きているという感じが伝わってきて、自分の心を解放してくれた。また、都心から日帰りできる自然にも魅力を感じ、水がきれいで山も森もあり、たくさんの農産物も生産されている南足柄に月に1回通うたびに、その環境のおかげで心が開いていく実感があった。
Eさんは、プログラムを修了してからも卒業生として運営に関わっており、コミュニティに関わり続けている。ほかに、山伏関係のコミュニティも重要である。コロナ禍の頃に日本の仏教や神道に興味を抱き、特に山伏への関心が深まったことから、山形県の羽黒山で山伏修行体験に参加した。二泊三日のプログラムで白装束を着て、滝行したり夜に山を歩いたりするなかで、自分を見つめ直したり自然と一体になる感覚を味わったりした。その後も、埼玉県の奥武蔵地域で定期的に山に入り、年に1回は山形から山伏の先達を招いて修行をおこなっている。
現在、Eさんはこれまでの経験を生かして起業し、いろいろな会社の社内業務についてITを活用して改善していく仕事を中心におこなっている。あるがままという意味の自然の然、型を破り続けて執着しないことを大切な教えとする禅、社会に善きことをしようと考えて善、これらの3つの意味を込めたZENを社名に入れた。これまで組織人として実践できなかったこと、マイナスとして捉えてきたところを翻し、それを力にすることができる社会に向けて動き出したところである。
以上の5人のライフヒストリーをもとに、コミュニティについて何か言えることがあるのか。それは別の機会に論じる予定なので、今回のコラムはここまで。
(松村正治)