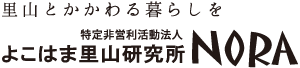第127回 岡田航『里山と地域社会の環境史』
2025.5.1雨の日も里山三昧
本書は、東京の郊外、多摩丘陵の一角に位置する八王子市堀之内地区の環境史であり、この小さな地域社会の歴史分析をもとに、これまでの里山論に欠けていた弱点を補う狙いを持って書かれた。ある郊外地域の環境史研究として、多くの史資料が広い視野から読み解かれ、読者が納得できるかたちで丁寧に綴られている。徳川幕府による新田開発、明治政府による入会林野の近代化、高度成長期の多摩ニュータウン開発など、強力な開発政策が地域社会に降りかかるなかで、人と自然の関わりにどのような変化が生じたのかが明らかにされている。
著者は、国レベルの政策に翻弄される地域住民の姿を描くだけではない。むしろ、従来の生き方や暮らし方が続けられなくなる大きな変動期であっても、地域社会にとって死守すべき「人自然関係」と「人人関係」を、ときには巨大な力に抗いながら維持してきた人びとの営みに注目する。たとえば、江戸末期には幕府から強いられる農地開発を拒んで秣場を守り(第一章)、明治初期には入会地の解体が迫られるなかで学校林を設置して林野の利用拡大を図った(第二章)。昭和から平成期に検討された農業公園構想に対しては、農地が単なる機能的空間となり、多面的な繋がりの総体が失われることを懸念し、消極的な態度を示した。(第三章)。しかし、その後の平成期の里山公園づくりでは、住民が主体的に保全管理に関われるように調整し、公園計画を受け入れた(第四章)。さらに、ニュータウン開発の進むなかで、地区内の五か所で伝承されているどんど焼きが五者五様に多様化してきた経緯が詳らかにされる(第五章)。
これらの事例を扱う各章は、どの文を取っても慎重に言葉が選び抜かれており、この地域に生きてきた人びとの心情に寄り添って歴史を紡ごうとする著者の誠実な姿勢が伝わってくる。このように、幕末から現代に至る一つの地域の環境史研究という点では、非常に充実した内容となっている。
ただし、本書の狙いは、ある地域の環境史を叙述するだけではない。著者は、「里山」をめぐる先行研究を適切に整理したうえで、それらの議論に地域住民の視点が欠落している点を指摘する。そのうえで、堀之内に生きる人びとの気持ちを代弁するかのように、新しい里山論として提示したのである。
里山論は、一九九〇年代以降、生態学、歴史学、民俗学、社会学などの分野をまたがって展開されてきた。そのなかでは、日本の生物多様性を保全する上で里山が重要な空間であること、その里山の維持管理を担ってきた地域住民が少なくなっていること、新しい担い手として地縁関係のない市民の参加が期待されること、しかし、市民参加による里山保全も実際はうまくいっていないこと、などが言われている。著者は、今日の里山問題に対して、大きな社会変動があっても里山との関わりを維持してきた地域住民の視点に学ぶ必要があることを説く。
また、堀之内における住民と里山の関係は、時代とともに変化し、再編され、新しいかたちで生活と結びつくという〈根ざしなおし〉が積み重ねられてきた。地域住民がそのようにして「人-自然関係」と「人-人関係」を自分たちが納得できるかたちで治め、それぞれの関係が「無事」であり続けるように願ってきた。このようにして住民が里山とともに生きてきた考え方やふるまいは、著者が主張するように、今後の里山保全に活かせるヒントになるだろう。
もっとも、こうした主張には首肯する一方で、本書の議論は、たとえば生物多様性の観点を重視する生態学の議論と交差する点が乏しく、対話の余地が限られる印象を受けてしまう。たしかに、従来の里山論では、地域住民が生活する空間のあり方について、住民の視点が希薄なまま議論が重ねられてきた面はあるが、その背景には担い手だった地域住民の減少があったのだ。この現実の重さを踏まえて先行研究を共感的に捉え直さない限り、新しい議論は生まれにくい。
近年、里山の生物多様性は悪化するばかりで、里山と関わってきた生活文化も急速に消失しつつある。こうした危機に対応するには、これからの里山がどうあるべきか、人と里山の関係をどう変えていくべきかについて、地域ごとに十分に議論していく必要があるだろう。今後の著者には、堀之内の住民に寄り添ってきた温かいまなざしさで、諸分野の知見と対話しながら新たな提案を生み出す里山研究を期待したい。
(松村正治)
※この文章は、ある書評誌から依頼されて執筆した書評の初稿である。