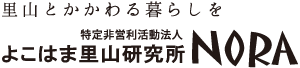神奈川・緑の劇場 vol.43
2025.1.29神奈川・緑の劇場

★阪神淡路大震災の30年目に★
=「食べもの通信の12月号」〝読者の広場〟に懐かしいお名前を見た。=
30年前に一度、ご一緒しただけなのに、兵庫県の方で、記事の内容から確信した。残念ながらお顔を覚えている訳では無い。ただ、明るく爽やかな雰囲気の女性で、胸がときめいたことまで思い出した。
淡路島へのフェリーのデッキから風に吹かれて眺めた瀬戸内海とともに。
=阪神淡路大震災がなければ、訪れなかった出会いだった。=
不謹慎な話だ。30年目の「食べもの通信」誌面ごしの〝再会〟。NORA横浜読者会を主宰して、誌面の隅々まで目を通していたから気がついた偶然。
=今日は1月17日。阪神淡路大震災から30年。=
救援物資を私が運んだのは2~3カ月経っていたように思う。まだ寒さの残る季節だった。
農民運動全国連合会(農民連)が設立されて、まだいくらも年数が経っていなかったころ、それでも全国の仲間たちの絆は強まっていた。
兵庫県農民連産直センターに神奈川農畜産物供給センター・生産者と消費者が手をつなぐ会の事務局として、救援物資を2トンのアルミバントラックに積んで、通常の業務が終わってからの、夜の出発だった。
農民組合神奈川県連合会の遠藤伴雄事務局長(故人)と、自然農法でぶどうやキウイフルーツを中心に育てる生産者、愛川町の諏訪部衛人氏の三人。
私は40歳。まだまだ元気だった。とはいえ、思い返せば、あんな強行な行程をよくやったものだ。
東名高速の途中の宿泊施設付きのサービスエリアで仮眠をとったが大阪から神戸までは大渋滞。眠気を必死でこらえて運転した。
兵庫の産直センターでは、全国各地から寄せられた米の袋の山を積み直して整理。何か働かずにはいられなかった。一緒に行った遠藤さんと諏訪部さんを先に神奈川に帰して、私は明石の小さな木造の家の鍵を渡されて泊めさせていただいた。
神戸からほど近いのに被害無し。直下型の大震災だった。
=翌日は淡路島へ。農民連震災被害調査団(小林節夫初代会長(故人)が団長)に加わる。=
まだ明石大橋はできていなかったので、フェリーで淡路島に渡った。淡路島では新聞記者さんと組んで割り当てられた被災地を廻った。
農業用の溜池が各所にあったが、震災で決壊して緊急に復旧工事中。黒くて厚手のシートを溜池の底面に敷き詰めていた。春になる。急がねばならない。農地には身長を超える高さの断層ができていた。
崩れ残って壁の無い柱だけの家の中に、ちょこんと座るおばあさんが、とびきりの笑顔で迎えてくれて話を聴かせて下さった。その姿が、せつなく、悲しかった。
苦しい、厳しい状況の時、人に話しをすること、支援者は話を伺うことの大切さを思う。
=神戸の市街地が横浜と重なって見えて仕方がない。=
神戸市街では、ビルや木造の建物が崩れた様子、高速道路が横倒しになった有様、液状化した港湾施設など、同じ港町、横浜の景色が重なって見えて仕方ない。それは30年経った今も続いている。容易に思い描くことができる。
特に、大火災で多数の人々が犠牲になった長田地区は、夜のJRの車内からは全く明かりが無く焼け残ったビルのシルエットが浮かび上がって見えるが、シンとして不気味だった。
焼け尽くされた様子は横浜と重なって見えた。横浜もこうなると思えてならなかった。
京浜急行の日の出町から井土ヶ谷まで、あるいは横浜から石川町までのJRの夜の車窓の景色が真っ暗で音の無い様子が想像できてしまうのだ。
=倒壊したビルの谷間の笑顔=
横浜ならば関内から日本大通りのような官庁街も、ビルが各所で倒壊していたが、アフターファイブの宵の口、勤務を終えたと思われる若い男女の笑い声、笑顔が広がっていた。
大小の野外テントが建てられ、テントの下は臨時の飲食エリアになっていた。今の私ならば、若い世代の間に入って話を聞くかもしれない。いや、実際はそんな体力は今は残っていない。
あの時は被災した人々の、現実と向き合う日々の逞しさに圧倒されて立ち尽くすだけだった。
日本の災害被災の歴史の大きな節目となった阪神淡路大震災の時の出来事である。
(2025年1月23日記三好豊)
・京都で振り売り(伝統的な農産物の移動販売)をする角谷香織さん→★★
・日本の農産物流通に3つの提案 神奈川野菜を届けて36年 三好 豊→■■ 三好 豊(みよしゆたか)
三好 豊(みよしゆたか)
“50年未来づくりプロジェクト”を提唱します。
“もりびと”が木を植えて育てるように、子どもたちが社会の真ん中で活躍する時代のために、今日できることを一つずつ。老いも若きも一緒になって50年のちの日本の景色を想い描きたい。
1954年に生まれ父親の転勤により各地で育ちました。 1975年10月、杉並区阿佐ヶ谷南の劇団展望に入団。1982年退団して横浜に戻り演劇活動に参加してきました。1987年5月、(有)神奈川農畜産物供給センターに入職し、県内各地、各部門の生産者に指導を受けることができました。2004年に退職し「神奈川・緑の劇場」と称して県内生産者限定の野菜の移動販売を始めました(現在終了)。NPO法人よこはま里山研究所・NORAの支援はたいへんに大きく、これからも都市の暮らしに里山を活かす活動の一環として生産者との関わりを大切にしたいと考えています。また(株)ファボリとその仲間たちとの繋がりには、心躍るものが生まれています。