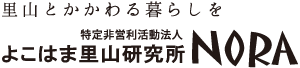神奈川・緑の劇場 vol.51
2025.9.30神奈川・緑の劇場

=ひとりひとりが〝朝ドラ〟の主人公に思える「食べもの通信」編集の皆さん=
NHKの連続テレビドラマを何十年ぶりかで観るようになったのは、週3回の透析クリニックでの透析中にリクライニングシートのベッドに備え付けのテレビをイヤホンで観るようになったから。
昨年の〝虎に翼〟に感動し、今年の〝あんぱん〟も、たいへんに楽しみになりました。加えて、9年ぶりの再放送〝ととねえちゃん〟。3作ともに戦前、戦中、戦後の価値観の大変容、激動の時代を生き抜く姿に、ささやかな日常描写の場面でも涙腺が緩んで仕方がなかったのは年のせいですね。
戦乱の果てに、主人公たちが人々の暮らしに役立つ雑誌づくりに奮闘する姿や、過酷な戦場を生き抜いた、やなせたかしさんの思いを込めた〝詩とメルヘン〟の発行の様子は、今年で創刊55年の〝食べもの通信〟の編集部の皆さんの姿と重なって胸に迫ります。「食べもの通信」に関わる皆さんひとりひとりが、〝朝ドラ〟の主人公に思えてなりません。
=家庭栄養研究会の提言=
「食べもの通信」は学校給食に携わる若い栄養士の皆さんが中心になって立ち上げた家庭栄養研究会が編集・発行しています。
誰にも忖度なく発言・報道するために広告に頼らず、読者の購読料で運営し、食品公害から子どもたちの健康と未来を守るために安全な食べものと自然のリズムに沿った日本の風土に根ざしたお米を中心とする食文化を大切に、食と「いのち」のつながりを学び、平和・環境を大切に食糧自給率を高めよう、と提言してきました。
=家庭栄養研究会・会員と読者減少で発行継続の危機=
今、戦後を活躍してきた多くの団体と同様に、家庭栄養研究会も世代継承に悩んでいます。また、SNS時代、〝紙離れ〟と言われる時代になって購読者の減少も重なり、発行継続の危機が迫っています。
しかし、若い世代が家庭栄養研究会が発信してきた提言に無関心とは思いません。むしろ、環境、健康、暮らし、戦争と平和、戦後生まれのどの世代よりも我がこととして強い関心があると思います。
実際に、熱心に学び、情報を広げ仲間づくりを進める若い世代にも何人も出会っています。
「食べもの通信」の読者からの便りを読むと、自身が病を経験して「食べもの通信」に出会った人。不確かな情報が溢れる時代に〝正確な情報を伝え続ける〟〝大切な情報を得ることができる〟〝作り手の心意気と心血注いで頑張っている姿が見える〟〝知りたかったことが1冊にある〟など次第に深く読み込んでいる読者も増えています。
=読者会をおすすめしています。気軽に始めてみませんか?=
私たちの、NORA横浜の読者会は常連メンバーは6人。お休み中の仲間を加えると10人くらいです。
毎月1回二時間のリモートで開催しています。新年になると70回を数えます。
2019年に2人でもいいから始めてみようとスタートしました。すぐにコロナでリモート開催するようになって、当初、意気込んでいた掲載レシピの料理を作って囲みながら、は出来なくなりましたが、宮崎やドイツなど遠方の仲間とも気軽に毎月会えるのも楽しみです。
回を重ねて、読者会が参加者の暮らしにかけがえなくなってきました。読み損ねたまま読者会の日が来てしまうことがあっても、さっと目を通しただけでも、仲間たちがピックアップした記事に各々が感想や体験を出し合って、理解が深まります。
情報トピックスや編集後記、読者のひろば=私もひとこと= などの小さな記事にも大事な情報や読者仲間の皆さんの思いが詰まっていて読むのが楽しみです。
読者会は話題のポイントを記事を軸にできて散漫になりません。難しい内容でも、楽しく読み続けられます。執筆者、編集部、読者仲間の皆さんとのつながりを身近に感じます。
家庭栄養研究会の会員になり、地方運営委員をお受けしたり編集部の会議にオブザーバー参加したりと、ますます私たちの大切な情報誌になっています。
=「創刊55周年記念日のつどい」への参加をお誘いします=
11月23日(日)14時~16時30分
会場:全国教育文化会館・エデュカス東京5階会議室
(JR・東京メトロ市ヶ谷駅・四ツ谷駅より7分、麹町駅より2分)
第1部
記念講演
信州在住・料理研究家
横山タカ子さん
「食べることは生きることー次世代に伝えたい食べ方・暮らし方」
第2部
連載執筆者との交流
参加費1000円
参加申し込みは家庭栄養研究会へ
住所・電話番号・氏名をつどいに申し込みとして
電話:03-3518-0624
FAX:03-3518-0622
メール
:kaeiken@tabemonotuushin.co.jp