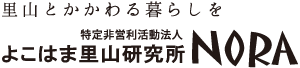神奈川・緑の劇場 vol.48
2025.7.1神奈川・緑の劇場

=食糧自給率向上は手遅れ、時代遅れ。耕作率100%こそ目指すべき!=その3
食糧自給率を高めようとする暮らし方の先に、体と心、社会の健康を求めることができる。絶望的で手遅れでも、やるしかない。
=五穀豊穣を神々に願い、豊作に感謝してきた日本列島の心を、私たちは忘れてしまったか?作物を金に換える〝商品〟としか考えられなくなってしまったか?=
米の在庫が底をつく端境期。七月、八月がやってきた。災害時など不測の事態の時に供出するはずだった〝備蓄米〟を、有料で売り渡して備蓄米の在庫を無くして端境期を迎える。九月には新米の収穫が本格化する、が、目論見通り新米は収穫できるのだろうか?記録的に早い梅雨明けになり、渇水は大丈夫か?いや、線状降水帯による記録的短時間豪雨による大洪水が心配だ。今年の台風は?豪雨と暴風で稲も野菜も吹き飛ばされる!気候が変わって以前はいなかった害虫が大繁殖する!病気も拡大する!……九月になって無事に作物が実るか、誰にもわからない。神のみぞ知る、だ。それでも作付けを続けてくれる生産者には深く深く感謝するしかない。
かつて、新米に手をつけるのは、正月からの祝いの膳だった。不測の事態に備えて前年の米を備蓄して、新米よりも先に利用していたのだ。
=食糧・農林水産業の復興は平和を守る道。世界の小規模家族農業者と連帯し、食糧主権、生存権を確立して自立した食糧政策を=
日本列島には日本列島に適した作物、農林水産業のやり方がある。現に、今も日本列島の各地で、営まれ、合わせて各地の豊かな食文化、土地に根付く祭りも伝わる。〝多面的機能〟と言われる国土を守り祖先から代々伝えられてきた。
それらの多くは1950年以降、目先の経済効率だけが注目され省みられることもなくなった。
だが、今、若者たちには注目されている。困難が待ち受ける若者たち、子どもたちの未来を拓く可能性を感じられるからだ。衣食住を石油製品から脱却し、自然に学び、自然に添った暮らし方ができる家族の在り方。農林水産業の現場には心豊かな人々のつながりがある。
(2025年6月30日記三好豊)
・京都で振り売り(伝統的な農産物の移動販売)をする角谷香織さん→★★
・日本の農産物流通に3つの提案 神奈川野菜を届けて36年 三好 豊→■■ 三好 豊(みよしゆたか)
三好 豊(みよしゆたか)
“50年未来づくりプロジェクト”を提唱します。
“もりびと”が木を植えて育てるように、子どもたちが社会の真ん中で活躍する時代のために、今日できることを一つずつ。老いも若きも一緒になって50年のちの日本の景色を想い描きたい。
1954年に生まれ父親の転勤により各地で育ちました。 1975年10月、杉並区阿佐ヶ谷南の劇団展望に入団。1982年退団して横浜に戻り演劇活動に参加してきました。1987年5月、(有)神奈川農畜産物供給センターに入職し、県内各地、各部門の生産者に指導を受けることができました。2004年に退職し「神奈川・緑の劇場」と称して県内生産者限定の野菜の移動販売を始めました(現在終了)。NPO法人よこはま里山研究所・NORAの支援はたいへんに大きく、これからも都市の暮らしに里山を活かす活動の一環として生産者との関わりを大切にしたいと考えています。また(株)ファボリとその仲間たちとの繋がりには、心躍るものが生まれています。