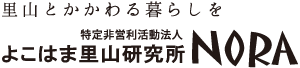神奈川・緑の劇場 vol.47
2025.5.31神奈川・緑の劇場

お米の価格高騰に関心が集まっているうちに、また激甚災害が心配な夏になります。森の動物たちは、今年も人里に、町に現れるのでしょう。獣の被害で作物を作れなくなった畑が荒れて山に戻っていきます。
農林水産業の問題は、日本列島に暮らすひとりひとりに関わる問題です。
=お米の値段=
江藤大臣が『米を買ったことは無い。』とホントのことを言って更迭されました。米を買ったことが無い人は日本には大勢いるのでは?米づくりする人が減って、米をいただける人も減っただろうけれど。
国会議員ともなれば、『おらえの先生におらえの米をくってもらうべえ』と米を届けてくれるでしょう。祝い事があれば米で作った酒を届けてくれるでしょう。それって日本の文化でしょう。それで更迭ですか。まあ、立場と時期があまりにも無神経な発言でしたね。
=食糧危機は低所得者から買えなくなっていく。すでに始まっています。=
富裕層は高騰した米は買う必要はありません。
たとえば、年間契約した生産者から安定価格で取り寄せています。有機農業で育てたおいしいお米でしょう。
あるいは田んぼのオーナーになって一定額を提供してできたお米を取り寄せる形式もあります。
自ら田んぼを借りて米づくりをしています。
富裕層は情報にも恵まれていますから、米不足になることを何年も前に見越して、自分は困らないように手を打っているのです。
それが、メディアの関係者ならば情報はしっかり入ってくるでしょう。メディアでの発信力もあるでしょうが、大事なことを国民には知らせてくれません。
実家や兄弟が米づくりをしていれば、やはり米は買いません。毎年、送られてくる米を楽しみに、誇りにもしているのです。
日本では、米も雑穀も野菜も年貢ではあったけれど、売る前に自給する作物でした。祖先から受け継がれてきた田んぼや畑は大切に守り、次の世代に引き継ぐものでした。
祖先からの、もっと言えば神々からの授かり物でしたから、採算が取れなくても、大切にしてきたのです。
週末に空き屋になった実家に帰って米づくりをする人に米の生産価格をたずねました。普段は考えもしなかったけれど、いろいろ考えて苦笑いされていました。もちろん利益などありません。諸経費は多額の持ち出しです。
自給的な米づくり、喜ばれることを糧に、兄弟、親戚への縁故米が日本では相当量あったけれど、それも高齢化や水源を維持できない(上流がやめると下流ができなくなる)などで廃田になります。
=米の価格を市場に任せるのは間違いです。=
ヨーロッパ並みに農業の担い手の所得保障を至急に始めなければなりません。作物の価格補償も必要です。農業の担い手は高齢化であと5年が限度と言われています。
スイスは100%以上の所得保障があります。すでに公務員状態です。ですが農林水産業とは国民にとってそういうものです。
林業を考えてみれば明確です。植林して手入れをして50年~80年育てなければ、木材として出荷できません。
世代を継承して、代々受け継がれるのが農林水産業です。
日本の林業は自給率が回復しています。円安で外材が高くなった影響ですが、担い手がいないのは深刻です。
日本の水産業も自給率が上がっています。水揚げは半減しているのに。日本の経済力が下落して、世界の水産物を買えなくなっているといいます。
=やっと、やっと、農業に関心が!=
米高騰・米不足で、連日、メディアやSNSは大騒ぎになりました。長年、日本の農業政策を批判し、農業崩壊、食糧危機が迫っていることの警鐘を鳴らしてきた人たちは、やっと多くの人々に農業への関心を持ってもらえたと、そして、多くの人々と一緒に、次の段階に自分たちも進まなければならないと、考えていることでしょう。
=〝非常時〟目が離せない世の中の動き=
刻々と世の中の状況は変わります。日本も、世界も何が起こるのか?
今は〝非常時〟です。精一杯、日々のニュースに注意していなければなりません。
今日は5月30日。トランプ関税交渉が4回目となり、日本が米不足のタイミングで、米や乳製品の輸入をアメリカに捧げるのではないか、と農業者は緊張しています。
すでに、つい先月に指摘した通り、米の輸入は始まっています。
安倍昭恵さんがロシア・クレムリンを訪問しプーチン大統領と面会しました。なぜ?今なのか?
敵対するイランとアメリカが交渉のテーブルに着くといいます。
ウクライナとロシアの停戦交渉が次の段階に向かうか?ロシアが最大の無人機攻撃をウクライナに加え、また新たな犠牲者を出したばかりです。
ガザではようやく搬入された支援物資に人々が殺到して死者が出たといいます。
この夏の気候災害を心配する中で、〝寒冷渦〟という言葉を初めて気象予報士から聞きました。極端な気温差に体調の維持が大変です。和歌山ではヒョウの被害で特産の梅に多大な被害が出てしまいました。
そして、学校給食や病院、介護・福祉施設や子ども食堂、重い学費を負担する学生や貧困世帯に、無料で提供するべき、しかし、すでに品質劣化が激しい〝備蓄米〟という古古米、古古古米がネット販売で最初に用意した分は瞬く間に完売。一部の店頭に2000円程度で並ぶといいます。これは高騰前の通常の価格です。
これらは、わずか一日の間の報道です。もちろん、消費税や年金、学費高騰・・私たちの暮らしや子どもたちの将来に関わる大事な様々な課題が山となり、目白押しです。
都議会議員選挙や参議院選挙が近づいています。選挙目当ての発言やパホーマンスにも注意しなければなりません。
=忘れては困る。頑張っている人たちのこと=
農業・食糧の問題では、米高騰の影で、話題にならなくなったのが有機農業・自然農法です。
学校給食の無償化を進める自治体や、学校給食を軸に地産地消・有機農産物を利用し、地域の循環する経済圏を創る取り組みが広がりつつありました。
規模の大小に関わらず、地方に里帰りしたり、移住して〝農的な暮らし〟を始める若者たちが増えています。40代、50代から農業を始める人もいます。
〝半農半X〟もよし。〝国民皆農〟ひとりひとりができることをやらなければ、そして急がなけば間に合いません。
高齢者でも、農作業・野菜づくりはできなくても、毎日、何を食べるのか、が大切な〝生産〟につながる行動です。
〝消費者〟ということばは疑問です。〝費やして無くする者〟。これからは、生産→流通→活用者〝活かして用いる人〟として自覚し、生産の循環に加わりましょう。
日本のみを考えて〝自給率〟を考える時代は終わりです。
世界は人口爆発し、水資源の枯渇、洪水、気候変動で、作物を作れなくなります。世界の大規模農場ほど、万一の場合のリスクは大きく、小規模な家族農業こそ、世界の食糧危機を食い止めるために大切だ、と国連が〝家族農業の10年〟を呼びかけたのです。
日本は人口減少で需要が減るから田んぼはいらない、効率の悪い小規模な畑はいらないという時代ではないのです。
地球上の人々全体のために日本列島の恵みを活かす時代がやってきます。その準備を急がなけばなりません。100億人の人類の食糧を日本列島だけで賄えるわけはありません。しかし、どれだけの人々の命を救えるでしょう。
神奈川県の食糧自給率は2%だそうです。わずかです。が900万人の県民の2%18万人の食糧を単純計算ですが、生産しているのです。
=農林水産業の復興=
戦後80年を費やして、日本の農林水産業を破滅に向かわせてきたことに、私たちは気が付くことです。そして、日本の農林水産業の〝復興〟を皆で始める時になりました。
=日本の食糧自給率が38%。自給率を高めるって可能でしょうか?=
50年、100年かかっても、私たちが自分たちの食生活を見直さなければできないでしょう。
今、日本の高齢者はパンが大好きです。子どものころ給食でパンを食べさせられてきました。残留農薬入りのアメリカの小麦のパンで、アメリカの戦略通り、今ではパンが大好きな高齢者が大勢いる国になりました。
肉や卵、牛乳も大好きです。それが健康で文化的な食生活と思わされてきました。今でも、学校給食に牛乳は定番です。
でも、早ければ、今年の9月。学校給食が始まる時には生の牛乳は不足します。
卵も高値になったままですね。でも、ゲージ飼いの鶏に生ませた卵です。〝平飼い〟ならば1個80円でも、これからは買えるかどうか。
戦後、アメリカの指導で、行き場の無かったアメリカの、飼料用のトウモロコシ、大豆を日本人に食べさせるために、畜産、酪農、養鶏を奨励し、大規模化してきたのです。飼料のほとんどを輸入しながら育てた牛や鶏で、私たちは、国産の肉・卵を食べ、牛乳を飲んでいると思っているのです。
日本の食文化の基本の大豆まで、アメリカに握られています。納豆、味噌、醤油、豆腐、きな粉、豆乳、まだまだきりがありません。
酪農は〝山地酪農〟と言って、放牧を基本に牧草で飼育する農場が生まれています。未来の日本の山の風景が変わることを夢に頑張っている生産者がいます。今ならば、1リットル1000円は必要ですが。
卵も、世界ではアニマルウェルフェア、動物の健康福祉を大切にという考えから身動きのできないゲージ飼いをいつまでもやっているのは日本ぐらいになってしまいます。
日本の、山地、森林の多い、しかし、水資源や気候に恵まれた風土にあった農林水産業のやり方を、もう一度考えてみたいと思います。農林水産業に参入できる人に頑張ってもらいたい。少しでも応援したいと思います。
農林水産業の担い手が家族とともに生涯を送れる所得保障・再生産できる価格保障は欠かせません。
=そして、地方コミュニティの再構築は農林水産業の復興とセットです。=
子どもたちの教育、医療、福祉、文化、娯楽・・
小さくても、自給的循環型経済圏のコミュニティを日本列島の自然に合わせて無数に構築することです。
各コミュニティで〝祭り〟が起こります。もちろん、伝統の〝祭り〟を引継ぎます。日本ならではの、欠かせない文化です。
日本列島に生きた人々を、幾世代にも渡って守ってきた神々と、共に暮らすことが、人々の幸せにつながるというのは、日本列島で暮らしてきた私たちに受け継がれてきた思いではないでしょうか?その思いは、土地に根付いた食文化とともに、健康な暮らしを子どもたちに伝えることになるのでしょう。
(2025年5月30日記三好豊)
・京都で振り売り(伝統的な農産物の移動販売)をする角谷香織さん→★★
・日本の農産物流通に3つの提案 神奈川野菜を届けて36年 三好 豊→■■ 三好 豊(みよしゆたか)
三好 豊(みよしゆたか)
“50年未来づくりプロジェクト”を提唱します。
“もりびと”が木を植えて育てるように、子どもたちが社会の真ん中で活躍する時代のために、今日できることを一つずつ。老いも若きも一緒になって50年のちの日本の景色を想い描きたい。
1954年に生まれ父親の転勤により各地で育ちました。 1975年10月、杉並区阿佐ヶ谷南の劇団展望に入団。1982年退団して横浜に戻り演劇活動に参加してきました。1987年5月、(有)神奈川農畜産物供給センターに入職し、県内各地、各部門の生産者に指導を受けることができました。2004年に退職し「神奈川・緑の劇場」と称して県内生産者限定の野菜の移動販売を始めました(現在終了)。NPO法人よこはま里山研究所・NORAの支援はたいへんに大きく、これからも都市の暮らしに里山を活かす活動の一環として生産者との関わりを大切にしたいと考えています。また(株)ファボリとその仲間たちとの繋がりには、心躍るものが生まれています。