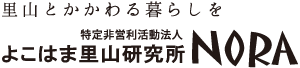第14話 Plastic Bag
2025.6.30わけ入れど谷戸はなお深く
皆さんにぜひ観ていただきたい短編映画がある。題名は「Plastic Bag」。Plastic Bag Short Film でネット検索すると、すぐ出てくる。通しで8分3秒だから、ちょっとひと息入れる時にでもどうぞ。内容は一言でいうと、“レジ袋の旅”を描いたものです。
レジ袋の旅
僕はその映像作品を森田真生さんの本で知った。※1 その本自体とてもおススメで、優しい語り口ながら決して気楽な内容ではないものの、でも僕は同じ時代にいる者として深く共感した。僭越ながら同行者の姿をとおくの稜線上に見とめた気分になった。
それで、「Plastic Bag」について。あちらの作品なのでナレーションは英語である。字幕なし。それでもあらすじは森田さんの本で紹介されてるので、おおむね理解できた。
物語は、スーパーのレジで一人の女性客が一枚のレジ袋を手にするところから始まる。袋はその女性を「創造主」と呼ぶ。二人?は何日か生活を共にし、そのあと、飼犬の糞を入れられたレジ袋は収集車で茫漠たる埋め立て地へ運ばれる。
風が吹く。袋は空に舞い上がり、長いあいだ村や街をさまよい歩く。一体どのくらいの時が経過したのか。すでに人間の気配はない。やがてレジ袋は海に出る。(紫外線の届きにくい海中では、プラスチックの分解はさらに遅くなる)
大海原のある場所でおびたたしい数の仲間とたゆたうレジ袋。さいごの場面で「創造主」にこう呼びかける。
― 私が死ねるように、私をつくってほしかった
エコバッグの中身
いちおう僕も若い時からエコロジストのはしくれのつもりなので、買い物には布製のいわゆるエコバッグを持ってゆく。ところが少々の食べ物や日用品を入れると、大量のプラスチック、ビニールの類でエコバッグは膨らむ。プラごみを せっせと運ぶ エコバッグ(修)行政によるプラごみ回収は週一回。当然、台所の片隅にあるプラ専用ごみ箱は溢れかえる。
さて僕の住んでいる佐渡は日本海の離島だから、特に西岸の海辺は漂着ゴミが目立つ。先日、松村さんの企画するZoom連続講座 ※2で、おなじ国境離島・対馬の海ゴミ状況を知った。かの島ほど継続的な取り組みではないかもしれないが、佐渡でも時どきボランティアによる清掃活動を耳にする。でも一時キレイになった浜はすぐにゴミまたゴミ。まさに現代版賽の河原だ。それに集めたゴミは焼却場で処理されるのだろうから、海ゴミは温室効果ガスとなって空ゴミに。文字通り始末にこまる。
毎日台所の片隅を、たまに海岸の光景を眺め、僕はただ始末に困る心地を抱きながら暮らしてきた。
プラごみは減る
一週間で溢れかえるわが家のプラごみ箱を、溢れない程度にとどめられないか。このごろようやくそんなことを思案しだした。さっそく具体的な方策が頭の中に並び始めている。この後実際にうまくいったり頓挫したりしてから報告します。
こんなことも想っている。僕が横浜から佐渡に移り住んで、四半世紀に近い時間が過ぎた。初めの頃は「大都市と離島の連携」的なステロタイプなフレーズが、流行歌の様に僕の中で鳴っていた。しかし結局これまで何もできなかった。
それでも今、そこはかとない予感のようなものがある。これからこの島の条件を活かして得心ゆく暮らしに近づけば、きっとそれだけ自分が生み出すプラごみも減る。そしてそんなことがもしできたら、遅まきながら僕は横浜の皆さんとも、あらためて一緒に何かできるのではないか。それぞれの強みを生かして。笑い合いながら。
何故かそんな気がしている。それが何故かはあとでわかればいい。
※1『僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回』森田真生 集英社 P.51~
※2 新時代アジアピースアカデミーNPA 環境運動のパブリックヒストリー
6/24 「 国境離島・対馬の海ごみ問題」
佐渡島在住 十文字 修