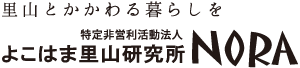第13話 谷戸で知ったこと ~その1
2025.5.31わけ入れど谷戸はなお深く
この連載の題にある「谷戸」について、そろそろ何か言おうかな。ぽつりぽつりと思い出すままに。ちなみに谷戸というのは僕の理解では、横浜市域を含め多摩丘陵あたり、広くは南関東で多く見られる行き止まりの小さな谷のこと。低地には田んぼが並び、奥の方には溜め池があったりして、さらに奥には水の湧き出る場所がある。斜面は雑木林、丘の上は畑。一般的な谷戸の姿はそんなところです。
谷戸とあのころの住宅地
僕が横浜市戸塚区舞岡町にある谷戸にどっぷり入り浸り始めたのは、23歳の時。1983年(昭58)である。同じ年に勤め人になったけれど、以降の休日はほとんどその谷戸で過ごした。そのうち平日でもそこで過ごすことが多くなった。なぜなら面白いことが沢山あったから。そのことをこれから、少しずつ紹介させてもらおう。思いつくままだから、途切れとぎれになるけれど。
その谷戸をぐるりと囲む住宅地は、新興住宅地と呼ばれていた(今もその呼び方はあるのだろうか)。当時、まだ造成されて20年足らずだったと思う。住んでいるのは全国各地に生まれ故郷のある、だから若い頃は農作業の経験ある人たちばかりだった。
ある時、その谷戸の荒れた休耕田を田んぼに復元することになった。すると普段はサラリーマンや専業主婦である新興住宅地の住人が、一人また一人と集まり始めたのである。休日のひととき、彼や彼女はふたたび鍬や鎌を握ってお百姓さんに戻った。
繰り出される知恵
一反(10a)のアシ原をひと冬で水田に復元した。全耕程を人力でやらかした。その冬から、頭だけエコロジー青年であった僕にとって、あたりの住宅地の住民達は師匠になった。
アシを刈りはらった後、全面積を鍬で起こす。鍬は振り下ろした後、テコの様に起こすと柄をいためるので土ごと手前に引き上げる。教えてくれたのは岡山出身の人。
使用後の農具をキレイにするには水路脇の草をむしり取って丸め、タワシ代わりにして水洗いする。これは宮城出身の人から。もちろん田んぼ仕事の一連の流れも。アゼを塗る、代掻きをする、苗代づくり、塩水選、芽出し、田植え・・・そして最後は餅つきまで教わった。あのころ横浜郊外の住宅地の中で地方が生きていたのである。
都市住民が、次から次へと農の技を繰り出してくる。これは僕には面白くて仕方なかった。数え上げればキリがない。ハゼ用に竹林で切った竹は、根元から垂直に抱き上げ、そのまま傾斜を歩き下る。抜けなくなった杭は、別の杭を斜めに沿わせて交差させ荒縄で縛り、それをテコにして抜く。足踏み式脱穀機の軸の奥に油をさすには稲の繊維を差し入れて、それに伝わせて油を少しずつ流し込むetc。
自由の方向
さっき面白くて仕方なかったと書いたが、何で面白かったかというと、ひとつには、少しずつ自分が自由になる気がしたから。
自分の身のこなし。自然の事物の利用法。他人の過ごしてきた時間の深み。そういった、何というか関係の取り結びのバリエーションが、都市の傍らに谷戸があったおかげで、それまでにない形で自分の中に宿る。日々そんな実感があった。目がひらかれる。それすなわち自由への途ではないかな。
いま、佐渡の山ふところの暮らしで、谷戸で得た知恵を使うことは多い。いつだったか地元の若い友人とわが家でお酒を飲んでいた。彼は佐渡の村々の活性化を論じる人である。月の明るい晩だった。ふと興がのって彼を庭に誘った。洗濯物を干す竹竿は、裏の竹林から伐り出したものである。僕は彼にその長い竹竿を肩で担いでみるよう促した。
あなたなら、どんな風に担ぎますか。
佐渡島在住 十文字 修