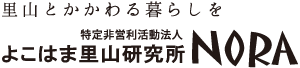雨の日も里山三昧

2023.2.1 第114回 石田紀郎『現場とつながる学者人生』
石田紀郎『現場とつながる学者人生』(2018年、藤原書店) 昨年11月から「環境運動のパブリックヒストリー」というタイトルで、市民向けのオンライン講座を開いている。 隔週で6回連続講座を開催して一区切 […]
2023.1.1 第113回 セルジュ・ラトゥーシュ『脱成長』
セルジュ・ラトゥーシュ『脱成長』(2020年、白水社) 年末も押し迫った12月27日の夜、私が担当している市民向けオンライン講座に、十文字修さん(いか福@Sado、元まいおか水と緑の会)をゲストに迎え […]
2022.12.1 寄り道59 プロボノと参加型デザインツールで団体紹介資料を作ってみた:a-con×NORA+Canvaプロジェクト
先日、NORAからのメッセージ15枚のスライドにまとめてリリースした。 タイトルは「Find My Satoyama」。 自然に関心はあってもきっかけがない、行動に移せないという人に向けて、自分の里山 […]
2022.11.1 寄り道58 コミュニティとコミュニケーション
先日、NPO法人こまちぷらすの寄付者向けの集まりに、ゲストとしてお話する機会をいただいた。 代表の森さんやファンドレイジング担当の佐藤さんとは知り合いだったものの、今回のお誘いをいただいたときは意外に […]
2022.10.1 第121回 遠藤邦夫『水俣病事件を旅する』
遠藤邦夫『水俣病事件を旅する―MEMORIES OF AN ACTIVIST』(2021年、国書刊行会) 著者は、1989年に水俣病センター相思社の職員となり、現在は理事を務めている。 本書は、水俣病 […]
2022.9.1 第111回 マッカスキル『効果的な利他主義』
ウィリアム・マッカスキル『〈効果的な利他主義〉宣言! ―慈善活動への科学的アプローチ』(2018年、新泉社) 横浜市からいただいている仕事で、NPOの組織基盤強化に関わっている。 NPOは、団体の目的 […]
2022.8.1 寄り道57 コロナ後の変わらなさへの対応―対話・チームづくり・マイプラン
コロナ禍の2年半の間に、私はライフスタイルが大きく変わった。 車に乗るようになったが、行動範囲は狭くなり、 アルコールを飲まなくなり、外食への関心が薄れ、 YouTubeで動画をよく見るようになった。 […]
2022.7.1 寄り道56 里山の市民科学とコモニング―6月の学習会を終えて
先月、2週にわたる連続学習会「ナラ枯れ被害の現在と皆伐更新の可能性―持続可能な里山管理を考える」をオンラインで開催した(主催:モリダス、共催:NORAほか)。 この企画は、倉本宣さん(明治大学)が中心 […]
2022.6.1 第110回 丸山・西城戸編『どうすればエネルギー転換はうまくいくのか』
丸山康司・西城戸誠編『どうすればエネルギー転換はうまくいくのか』(2022年、新泉社) 本書の2人の編者や論考を寄せている数人の執筆者とは研究上の付き合いがあるので、 刊行直後にご恵贈いただくことがで […]
2022.5.1 第109回 羽田康祐『地図リテラシー入門』
羽田康祐『地図リテラシー入門―地図の正しい読み方・描き方がわかる』(2021年、ベレ出版) 今年の2-3月は年度末までに引きうけた仕事が時間的にも能力的にも大変で、しばらく心をなくしていた。 4月に入 […]
2022.4.1 第108回 ハンナ・アレント『責任と判断』
ハンナ・アレント『責任と判断』(ちくま学芸文庫、2016年) 2020年7月から、南房総で地域づくりに関わっている人たちが中心になって開いているオンライン読書会に参加している。 なぜか通信手段にはLI […]
2022.3.1 寄り道55 いのちを想う
2022年2月21日、ロシアのプーチン大統領はミンスク合意を一方的に破棄し、 24日にロシア軍はウクライナ侵攻を開始した。 武力による現状変更は国際法違反であり、断じて許せない。 一日でも早くウクライ […]