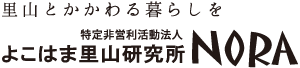06月27日 (金)|多摩丘陵の里山フォーラム夜会レポート
多摩丘陵の里山フォーラム夜会~「地域の人と自然をつなぐ」をテーマに 本音で語るネット座談会
日時:2025年6月27日(金)19:30-21:00
形式:オンライン(Zoom)
出演者:
- 田村薫さん(多摩グリーンボランティア森木会)
- 小林健人さん(NPO法人NPOフージョン長池)
- 後藤洋一さん(まちだみどり活用ネットワーク)
- 吉武美保子さん(NPO法人新治里山「わ」を広げる会)
- <進行>松村正治(モリダス、NPO法人よこはま里山研究所)
参加費:無料
参加申込者:47名
主催:モリダス、共催:NPO法人よこはま里山研究所(NORA)
令和6年度「緑と水の森林ファンド」助成
アンケート結果
本フォーラムを総合的に評価してください。
- とても良かった 82%
- 良かった 18%
本フォーラムをふりかえり、ご感想やご意見などを自由にご記入ください。
- お話を伺っていて、小林さんのように生物マニアが転じて里山(公園)の管理運営にかかわるようになった人材は本当に貴重だとあらためて感じました。ご本人は環境教育は身近な材料でもできると仰ってしましたが、そこに真正性が宿る気がします。また、モニタリングという実利的な意味でも重要です。
- 私は森木会(多摩)に所属するものですが、各地に類した活動をされている方があることを知れてとても刺激になります。
- 諸々の社会環境変化が環境固有の問題を更に難しくしていると思料します。ケースによるアプローチの選択肢と其々のベストプラクティスを見出したい。
自分の参加団体では、メンバーの参加目的が皆異なる。マネジメントが効かず難しいと見ている。特に高齢比率が高いと硬直化傾向に拍車がかかり、目的が健康維持で安全志向が強度になると、重要なスキル獲得作業を外注しがちになってしまう。軽作業のお茶のみクラブになり、物足りなさから新入者が定着しない。
高齢者以外の参加者意識、定着が課題と認識。世代による選挙行動と同じ傾向。なかなか難しい状況。 - 6月1日の総合人間学会での里山フォーラムでの講演の皆さんから引き続きお話を聞くことができ、親近感がありました。また、「身近な自然」について、場所が近いだけでなく、日常生活の一部として実際に自然に触れる関わるということの「身近」について考えるきっかけになりました。貴重な機会をありがとうございました。
- 地に足のついた、リアルな現場の状況が聞ける機会は貴重なので、ありがたかったです。
- 植物、昆虫に興味がある所から森の保全に関わってきたので、お話を聞いてとても共感しました。
最近よく見られる昆虫の名もいくつかでましたが、木もれびの森でもすべて確認していることから、ナラ枯れによる流れと私も思いました。森の管理は楽しいですが、色々と大変なこともあるし、自分もまだまだ勉強不足で焦ります。大変貴重なお話をありがとうございました。頑張ります! - 印象に残ったこと。新治で、ボランティアのお仕事があるということ、利用者の行動規制をしなければならない場面があること。ボランティア育成として、通年の講座に定着の効果がある。市民が利用、実践できる場として公園を位置づけること。登壇者に、専業的な方と、ボランティアの立場がある方とがあったこと。ナラ枯れが落ち着いてギャップができたいま、調査が必要とのこと。吉武さんから、マナーブック集的なものを配布しているというお話がありました。探して、各施設の利用案内の一部にそれぞれマナーページみたいなものがありましたが、ほぼマナー集みたいなものがあったら、紹介いただけると助かります。良い機会をありがとうございました。
- 本日は貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。録画で拝聴しまたが、多摩丘陵はじめとする様々なフィールドの取り組みの様子など興味津々で、あっという間の時間でした。草本変化やルイソホソカタムシのお話などもあり、初心者の私も楽しめるお話でした。
- 登壇者の方々の一つ一つのご発言が、ためになる・心に沁みるものでした。
街の中の緑を利用して、人のつながり・心の豊かさを深めるような活動を考えていけばよい指針を再確認することができました。ありがとうございました。 - ナラ枯れも自然なこと、管理する方たちの大変さとそれでも自然とつながっている喜び(長池公園のブログを読ませていただきます)を知ることができて良かったです。
- 私は礫河原で45年間研究してきたのでナラ枯れを契機にして森林が減少し、流域からの土砂流出が回復することを期待しています。里山の森林生態系が減って、草地や裸地ができることを評価する立場です。カワラノギクプロジェクトで、多摩川の礫河原の回復には1万年かかると言ってきたのですが、ほんとうに回復するかもしれないという期待を持てるようになりました。